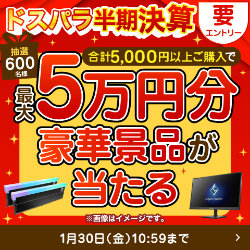※当ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
なぜPCケースには「木製」が少ないのか?素材選定の裏にある技術的・構造的な理由

PCケースといえば、スチールやアルミといった金属製が一般的です。
一方で、温かみやインテリア性を重視するユーザーの中には、「木製のPCケース」を愛好する方々もいます。しかし木製ケースはとても少ないですよね。
近年では一部メーカーから木材を取り入れたモデルも登場していますが、依然として主流にはなっていません。
そこで今回は、PCケースにおいて木材が採用されにくい理由を、技術面と実用性の観点から解説しつつ、実在する木製ケースの例も紹介します。
冷却性能と熱伝導の壁~木材は“熱を逃がせない”素材
木材は、金属と比較して熱伝導率が非常に低い素材です。
PC内部は、CPUやGPUなどの高発熱パーツが集約されており、これらの熱を効率よく逃がすためには筐体そのものの放熱性も重要です。
金属製のケースは、表面全体がヒートシンクのような役割を果たし、熱を自然放出する手助けをします。
一方、木材は断熱性に優れているがゆえに、内部の熱をこもらせてしまい、冷却ファンやエアフロー設計に頼る比率が高くなります。
これは、冷却効率を重視するゲーマーやクリエイターにとっては致命的なデメリットになり得ます。
電磁波遮蔽性能の欠如~EMI対策が不十分になりがち
もう一つ見落とされがちな要素が、「電磁波遮蔽(EMI)」の問題です。
PCは動作中、各種電子部品から微弱な電磁波を発します。これをケース内で抑えることにより、周囲の無線通信機器への干渉や、PC自体の誤動作を防いでいます。
金属ケースは、この遮蔽機能を素材そのもので自然に担保しています。対して木材は非導電性であり、電磁波をほぼ透過します。
木製ケースを採用する場合は、内部に金属メッシュを貼るなどの追加処理が必要になることがあります。つまりひと手間加えなければ、金属製ケースと同様のEMI対策ができないということですね。
加工の難易度とコストの問題──量産には不向きな素材
木材は、形状の自由度や接合の精密性において、金属よりも加工が難しい素材です。また、強度の確保が難しい素材でもあります。
同じ厚みの金属であれば強度を維持できても、木材ではそうもいきません。結果として筐体が大型化・高重量化しやすくなります。
また、湿度による膨張・収縮や経年劣化の影響も無視できません。これらの不確定要素から、量産や品質安定が求められるPCケース市場において、木材が敬遠されることが多いのです。
燃焼性と安全性の課題はあれども一定の数は存在する
電源トラブルやコンデンサ破損など、PCにはごくまれに発熱事故が起こる可能性があります。
金属ケースであれば構造的に火災の広がりを防ぐことができますが、木材は可燃性があるため、火元の周囲に引火するリスクを高めてしまいます。
このような万が一のリスクを考慮すると、特にBTOメーカーなどが木製筐体を採用するハードルは高くなります。
それでも、木製PCケースはニッチ市場において一定の需要があります。
たとえば、Fractal Designの「North」は、フロントパネルに木材を採用し、北欧家具のような高いデザイン性を実現しています。
また、CYBERWOODシリーズなど、DIY愛好者向けにパネル自作キットを提供する例も増えつつあります。
これらは、「インテリアとしてのPC」「静音性重視」「空冷+低発熱構成」など、明確な目的を持つユーザーに向けて開発されています。
ただし、やはり冷却構造の工夫やEMI対策の実装が前提となっており、全方位に対応できる“万能型ケース”としての木製採用は難しいのが現実です。
木製PCケースは魅力的だが、技術的制約が重すぎる
木製PCケースは、デザイン性やインテリア性において確かに魅力があります。
しかし、熱・電磁波・加工性・安全性といったPC筐体としての基本要件に対し、どうしても技術的ハードルがつきまといます。
そのため、現時点では「主流」とは程遠く、「趣味性の高い選択肢」としての立ち位置にとどまっています。
少なくとも現在の技術水準では、PCケースにおいて木材は“実用性より美学を重んじる”ための素材といえるでしょう。
今後、断熱性を補う設計手法や、木材と金属をハイブリッドした新素材が登場すれば、再評価されるかもしれませんね。