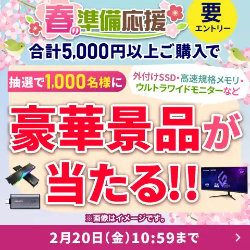※当ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
ネットがない時代に調べ物はどうやっていたのか ~スマホ世代が知らない情報探索の原風景~

今や検索すれば何でもわかる時代です。しかし、1990年代以前にはネットもスマホもなく、人々は別の方法で調べ物をしていました。
それでも、知りたいという気持ちと手間を惜しまない姿勢が、情報との深い向き合い方を支えていたのです。そこで今回は、ネット以前の代表的な調べ物の方法を紹介しながら、現代のリサーチとの違いを考察していきます。
本や辞書で調べる
なんといっても調べものの王道は「本」ですね。ネット以前の「検索エンジン」とも言えるのが、百科事典や国語辞典などの書籍です。
五十音順や索引をもとに知りたい言葉や現象を探し、該当ページを開いて内容を読んで理解するという手順が一般的でした。情報は体系的に編集されており、網羅性と信頼性の高さが特徴でした。
ただし、情報の更新頻度は低く、最新の情報には対応できない点が課題でした。基本的に本が更新されるのは短くても年に1度なので、現在のようにリアルタイムで情報が更新される時代ではありません。
現代との違いは、情報にたどり着くまでの時間と手間、そして一度に手に入る情報量ですね。Google検索では数秒で何十件もの情報にアクセスできますが、辞書では1ページずつ目を通す必要がありました。めっちゃ面倒ですね。
図書館に通う
情報収集の拠点として、図書館は欠かせない存在でした。
本の背表紙を見て並ぶ棚を探し、目当ての本を借りて読むというアナログな方法でしたが、その場でコピーをとったり、カウンターで専門知識のある職員に相談したりすることで、深い情報にアクセスできました。情報の質は高く、特に学術的な調べ物には有効でした。
ネットとの最大の違いは「移動」と「人的サポート」が必要な点です。自宅で検索できる今と比べ、調べ物には時間も体力も必要でした。
しかし、そのぶん「なぜこれを調べたいのか」という目的意識が明確になるという面もありました。なんとなくネットサーフィンしていて、余計な情報に触れるという時代ではなかったのです。
新聞や雑誌を読む
「リアルタイム性」という意味では、新聞や雑誌が優れていました。特に世の中の動き(時事・トレンド)を知るには、新聞や雑誌をさかのぼって読むのが一般的でした。
特に新聞の縮刷版は、図書館に通う調べ物の定番ツールで、当時の空気感や報道姿勢まで感じ取れる資料でした。トレンドや世論を理解するには雑誌も欠かせず、週刊誌から専門誌まで読み比べて分析することもありました。
ネットニュースと比べると、速報性や検索性は劣るものの、背景を深く知ることができたわけですね。紙媒体は「流し読み」よりも「読み込む」行為に近く、断片的ではない情報の読み取りが求められました。
人に聞く・電話で尋ねる
辞書にも載っていないようなことは、詳しそうな人に聞くのが一番の近道でした。学校の先生や専門職の人、時には電話帳で業界団体を探して問い合わせることもありましたね。
人の知識に頼るぶん、信ぴょう性は話す相手に左右されましたが、本には載っていない一次情報や裏話に触れる機会が多かったように思います。検索よりも「人間関係」や「信頼」が重要になる点が、現代のリサーチとの大きな違いです。
また、知ることそのものが「人とつながる手段」として機能していた時代でもありました。
情報量の違いと、「調べる」という行為の重み
現在の検索は、数百万件の情報が瞬時に手に入る反面、ノイズも多く、真偽の判断が求められます。
ネットがない時代は、情報量が限られているからこそ「この一冊に書いてあることは本当だろうか」と疑う余地が少なく、出典の信頼性が重視されました。
また、調べ物に時間と労力がかかるぶん、「本当に知りたいこと」しか調べなかった傾向があります。情報との向き合い方そのものが、今とは質的に異なっていたのです。
情報探索という意味では現在ほど恵まれた時代はない
ネットがなかった時代の調べ物は、情報への到達に時間と手間がかかる一方で、確かな情報や深い理解を得る手段でもありました。現代のネット検索は便利で高速ですが、その分だけ情報を「軽く扱ってしまう」リスクも抱えています。
あえて本を開く、図書館へ足を運ぶ、人に尋ねる。そんな「面倒」な手段が、知ることの意味を深くし、知識を自分のものにする力を育てていたのかもしれません。
しかし、単純な利便性やスピードという意味では現在の「検索」が最強ですね。特にPCの場合は検索と情報加工、発信をほぼ同時にできてしまうので書籍や図書館よりも圧倒的に優れています。