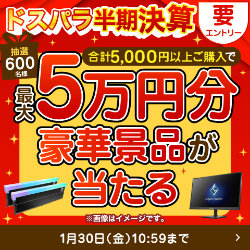※当ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
ネトゲあるある!なぜ古いゲームほど生き残るのか

ネトゲ(MMORPG)には、驚くほど長い運営期間を誇るタイトルが数多く存在します。
一般的に、リリースから数年以内にサービスを終了するゲームもある一方で、20年以上もの間、多くのプレイヤーに支持され続けているタイトルもあります。
近年はこの傾向が特に顕著で、いわゆる「二極化」が起きている印象です。今回は、「古いゲームほど生き残る」という謎の事象の原因をまとめてみました。
ネトゲ(MMO)は運営期間が長いタイトルが多い
ネトゲの世界では、一定数のプレイヤーを維持し続けることができれば、サービスが長期化する傾向があります。
これは、MMOがプレイヤー同士のコミュニティやゲーム内の経済システムによって支えられているためです。
プレイヤーがゲーム内で築き上げた関係性や投資(装備やアイテムなど)が大きいほど、離脱率が低くなる傾向があります。
さらに、長期間運営されているタイトルは、運営会社がプレイヤーの意見を反映させる形で改良を続けてきた結果として、プレイヤーからの信頼を得ています。
これはタイトルが短期間で終了するリスクを回避するための重要な要素となっています。
2000年~2010年にリリースされたタイトルは生き残り率が高い
まずはここまでが一般論なのですが、実際には「あまり評判がよくないゲーム」でも生き残っているんですよね。
そこでもう少し詳しく見ていくと、特定の年代、つまり「2000年~2010年」に勢いがあったゲームほど生き残りやすいというパターン見つかりました。
たとえば、日本国内では「ファイナルファンタジーXI」(2002年)や「ラグナロクオンライン」(2001年)、「モンスターハンター フロンティア」(2007年)、「ドラゴンクエスト10(2012年)」などがその代表例です。
これらのタイトルは、インターネット接続環境が普及し始めたタイミングで登場し、多くのプレイヤーにとって「初めてのオンラインゲーム体験」を提供しました。
また、当時のMMOはソロよりも協力要素を重視し、プレイヤー同士の協力やコミュニケーションが必須のデザインであったため、深いコミュニティが形成されました。
こうしたゲームは、単なる娯楽以上の「体験」としてプレイヤーの記憶に残り、時間が経っても一定の支持を集め続けています。
古いタイトルは「新規」よりも「復帰者」で成り立っている
長寿タイトルでは、新規プレイヤーの獲得よりも、かつてプレイしていた「復帰者」の存在が重要な支えとなっています。
復帰者とは、一度ゲームを離れたものの、時間を経て再び戻ってくるプレイヤーのことを指します。
古いタイトルでは、かつてのプレイヤーが懐かしさを感じて戻ってくる仕組みが整備されています。これは「いろいろなゲームを経験し、最終的に初めて体験したゲームに戻る=回遊現象」があるからだとか。
実際に古いネトゲの多くは、復帰者向けのログインボーナスや、過去のストーリーやキャラクターに関連する特別イベントを開催することで、プレイヤーに再び興味を持ってもらえる工夫を行っています。
また、復帰者はゲーム内での経験値や知識が豊富であるため、現役プレイヤーにとっても大きな戦力となります。
結果として、ゲーム内のコミュニティが活性化し、新規プレイヤーが少なくても安定した運営が可能になります。
長く遊びたいなら「古いネトゲ」のほうが適しているかも?
古いMMORPGが生き残る理由は、単に運営期間の長さだけでなく、プレイヤー同士の絆やコミュニティ、そして復帰者をうまく取り込む運営方針にあります。
また、2000年代に登場したタイトルは、技術的にも当時のゲーム体験として完成度が高く、多くのプレイヤーの記憶に深く刻まれています。
こうしたゲームは、単なる過去の遺物ではなく、今なお多くの人々に楽しみとつながりを提供し続けているようですね。
よくネットで「長く遊ぶなら?」というような質問を見かけますが、単純に細々とでも続けたいなら古いネトゲのほうが優秀かもしれません。
かなりマイナーなゲームでも生き残っていますし、古参プレイヤーの多くがかなり優しく親切ですし。
ゲームシステムやグラフィックはさすがに古いのですが、これらと「面白さ」は別ですからね。運営期間10年超のタイトルのみに絞って探すのもアリだと思います。